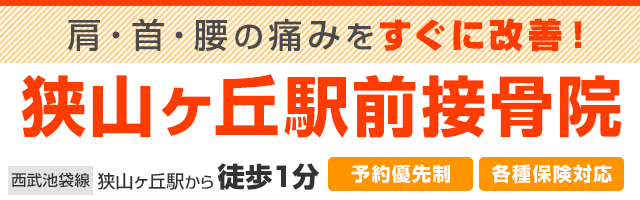テニス肘


スポーツ時の痛み
テニスのバックハンド時の痛みが生じます。
短橈側手根伸筋の起始部での肘外側で障害されて発生します。
物をつかんで持ち上げる動作をすると、肘の外側から前腕にかけて痛みが生じます。
短橈側手根伸筋、長橈側手根伸筋、総指伸筋の重なる外側上顆に起始している部分に負担がかかり、物をつかんだときや、ドアノブをひねる動作などで痛みが生じます。
年齢によって、40代以降で発症する人も多い、人間の身体は歳を重ねるにつれ、ゴムのようなしなやかさがなくなり、腕の筋肉も硬くなり、20代の時と同じ負担が掛かってしまうとちょっとした手首の使用頻度や強さは変わっていないけれど痛みが生じます。
テニス肘に関する当院の考え

テニス肘は必ずしもスポーツをしている人に起きるものではありません。日常生活上で慢性的に手関節の背屈時のストレスが加わるような動作で起きることもあり,35〜50歳代後半に多く加齢による肘関節外側の筋肉や腱の変性、また加齢などによる衰えも一因として考えられます。原因となる筋肉への負担を減らすことが大切になり、痛みを伴う動作を避け肘への負担を避けることが必要になります。スポーツが原因になる場合は症状を悪化させないために、一定期間休みを取ることで早期回復につながります。スポーツ障害・外傷の予防として全般的にウォーミングアップが重要でありウォーミングアップにより体温が上昇しさらに各筋肉への血流が増加することにより、スポーツパフォーマンスに効果的な迅速で強力な筋収縮が得られ、さらに障害の予防にもつながります。
テニス肘を放っておくとどうなるのか

テニス肘は、放っておくと症状がどんどん進行してしまうことが多い疾患です。肘の外側、肘と前腕をつなぐ筋肉の腱に過度な疲労が蓄積され、炎症が起きている状態です。初期症状は手関節背屈時やラケットのグリップ時に肘から前腕の痛みや外側上顆付近の圧痛があり、熱感を有する場合もあります。日常生活を問題なく送ることができるため、放置すると痛みが引かなくなります。より悪化すると握力が弱くなりコップを握るのも難しくなり、肘の曲げ伸ばしが制限されなど、日常生活にも支障が出てきます。重症化してしまうと治る期間も長くなり、保存療法では治せなくなり観血的療法を行う可能性も出てきます。そのため早期に施術改善することが大切です。
テニス肘の改善方法

痛みを感じるようであれば痛みの出る動きはしないようにして、湿布や消炎鎮痛薬などを肘の外側にアプローチすることで痛みが緩和してきます。痛みが出ていると言うことは炎症が起きているということなので、アイシングをすることにより血流量が減少し、痛みがなくなります。スポーツをし続けたい場合は肘用バンド(テニスエルボーバンド)を巻いてスポーツを行っても良いかもしれません。テニスエルボーバンドはスポーツ活動時に装着することにより痛みの負担を軽減する効果があり、プロのスポーツ選手も試合中に装着しています。患者様でも簡単に装着できて便利なものになっています。
テニス肘の改善にオススメする当院の施術メニューとは

初期の施術では、動かさないようテーピングやテニスエルボーバンドで痛みを軽減できます。当院での施術では、まず手技療法で前腕の筋肉をほぐしていきます。当院のメニューに手の極みというものがあります。この施術は特殊なオイルを使用して血流を促進していくことで痛みの物質を流し老廃物として除去していく施術で浮腫みも改善できます。この他にEMSという電気療法で腕に電気を当て筋肉にアプローチすることにより筋肉をほぐすことにより痛みを取っていきます。さらに肘に負担がかかるということは全身的・根本的にアプローチするために全身矯正を行い、骨盤の歪みを取ることにより全身を使えるようになり肘への負担を減らすことができます。
その施術をうけるとどう楽になるのか

施術後は手の重だるさや痛みが取れるか、ないしは和らぎ、動きやすくなったり今まで痛みが出ていた動きをしても痛みが出にくくなることもあります。手の極みをすることによって浮腫みや手の腫れも引き、筋膜が剥がれ血行を促進し疲労回復効果があり、動かしやすくなります。日が経つにつれて、痛みが戻ってくるため何回か通う事になります。一回の施術で完全に治すのことは難しいですが、その施術を何回か続けていく内に手の重だるさや痛みがなくなる方が多いです。
軽減するための施術頻度は

テニス肘は保存療法を行うことは可能ですが、症状の重さによって異なる場合があります。軽度であれば比較的早く完治しますが、症状が進行してしまっていると3ヶ月ほど安静にしなければなりません。最低でも3ヶ月間は行い、頻度としては週に3回通って頂く形になります。軽症ですと1ヶ月〜1ヶ月半、重症ですと3ヶ月は必要です。スポーツを行いながらになると週に4回通って頂き、テニスエルボーバンドを装着しながらになります。状態によっては観血療法となることもあります。対策として過剰な運動をさせないように練習量と運動動作を見直しなどの管理が必要です。