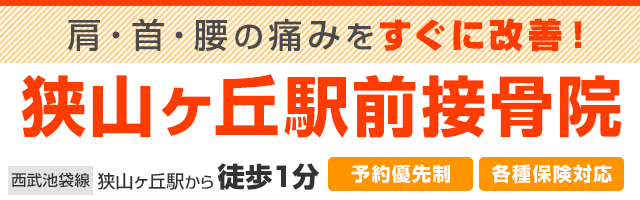巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

人から猫背といわれる
肩が重だるい
起きる時に背中が重く、固まっている感覚がある
何もしてない時でも身体に力が入ってしまったりリラックスが出来ていない
腕を上げようとしても肩が動かなくてうまく上げられない
巻き肩について知っておくべきこと

肩こりは、背中の筋肉(僧帽筋)が弱くなっている状態といわれています。普段から肩が内側に入る姿勢(猫背)や、肩が下がってしまう姿勢(なで肩)の方は、肩こりが起こりやすい傾向があります。
このような姿勢を繰り返すことで、肩甲骨の位置が正常な場所よりも外側・下側・上側へと引っ張られてしまうことがあります。肩甲骨が引っ張られると、背中の筋肉(僧帽筋)も一緒に引っ張られて負担がかかり、筋肉が硬くなって血流が悪化します。その結果、酸素や老廃物の循環がうまくいかず、「肩が痛い」「だるい」「重い」「違和感がある」「動きにくい」など、さまざまな症状につながっていきます。
また、肩の筋肉が硬くなると首にも負担がかかるため、頭痛の原因になることもあります。
症状の現れ方は?

肩まわりには多くの血管が通っており、筋肉が伸び縮みすることで血液循環が促進され、全身へ酸素や栄養が運ばれます。しかし、腕の重みや頭の重さなどによって肩の筋肉に過度な負担がかかると、筋肉が硬くこわばり、血管が圧迫されて血流が悪くなります。その結果、乳酸などの疲労物質が蓄積し、神経を刺激してこわばり・だるさ・重さといった肩こりの症状が現れやすくなります。
肩こりが慢性化すると、さらに筋肉の緊張が強まり、肩甲骨が前方へ引っ張られることで肩が内巻きになり、血行不良が続く悪循環に陥ってしまいます。
その他の原因は?

肩こりが悪化すると、肩だけでなく鎖骨・肩甲骨・首などの周辺筋肉の血流が悪化し、首の可動域にも制限がかかることがあります。さらに進行すると、肩関節に炎症が生じ、腕を肩より上に上げづらくなり、「四十肩」や「五十肩」のような症状が現れる可能性もあります。
また、肩こりが原因で目の疲れを感じる方もいます。これは、目の奥にある筋肉が自律神経と関係しているためで、自律神経の乱れがうつ状態や自律神経失調症などにつながる場合もあります。自律神経が乱れると、めまい・頭痛・吐き気などを引き起こすこともあるため、肩こりの症状を放置せず、早期に軽減を図ることが大切です。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、肩甲骨の周囲にある筋肉が常に引っ張られた状態となります。この状態が続くことで血流が悪くなり、新陳代謝が低下しやすくなります。
新陳代謝の低下によって、胃腸の働きも鈍くなり、消化不良や便秘などが起こりやすくなるほか、基礎代謝も落ちるため、肥満につながる可能性もあります。全身の筋肉も硬くなりやすく、肩だけでなく腰や膝まわりにも負担がかかり、痛みを感じるリスクが高まります。
また、肩まわりの筋肉が硬くなることで首にも負担がかかり、首の筋肉が硬くなることにより、頭痛を引き起こすケースもあります。さらに、上半身の前側(腕・脇・胸)の筋肉を使いすぎ、背中の筋肉がうまく使われないと、手や腕にしびれが出る可能性も考えられます。
当院の施術方法について

患者様それぞれの症状の重さや肩こりを抱えていた期間などにより、軽減にかかる時間には個人差があります。そのため、施術の頻度についても患者様ごとにご案内が異なります。
【マッサージのみの場合】
マッサージのみでは1回の施術による変化は比較的少ないため、毎日または1日おきのご来院をおすすめしております。
【マッサージ+矯正施術の場合】
マッサージに加えて矯正施術を行うと、1回の施術による変化がより大きくなるため、2~3日おきの通院を推奨しております。早めの変化をご希望の場合は、毎日通院されることでスピードも期待できます。
【マッサージ+矯正施術+αの場合】
当院では、電気施術や鍼施術など多様なメニューをご用意しております。これらを併用されることで、1回ごとの変化がさらに高まり、週に1〜2回のご来院でも十分な効果が期待できます。もちろん、それ以上の頻度でのご来院も可能です。
軽減していく上でのポイント

肩こりの多くは、日常の姿勢の乱れが大きく影響しています。上半身の前側の筋肉(胸・腕・脇)と、背中側の筋肉とのバランスが崩れることで肩甲骨の位置がずれ、僧帽筋などの背中の筋肉が引っ張られて肩こりにつながることがよくあります。
そのため、以下の3つのポイントが大切です。
1、肩甲骨の動きをよくすること
悪い姿勢を続けると肩甲骨とその周囲の筋肉が硬くなってしまいます。胸を開いて腕を開くストレッチ、腕を上げてから引く動作、肘を後ろに引くような運動などが、肩甲骨の可動性を高めるのに役立ちます。
2、前側の筋肉を緩め、背中の筋肉を強化すること
前側の筋肉(胸・脇・腕)を緩めるにはマッサージが効果的で、ストレッチを加えることで変化がより早まることが期待されます。背中の筋肉は、動かすだけでなく、力を入れた姿勢を10秒ほどキープするトレーニングなどが効果的といわれています。
3、背骨の丸まりを整える姿勢作り
普段から胸を開いて背筋を伸ばし、お腹に軽く力を入れるような姿勢を意識することが大切です。