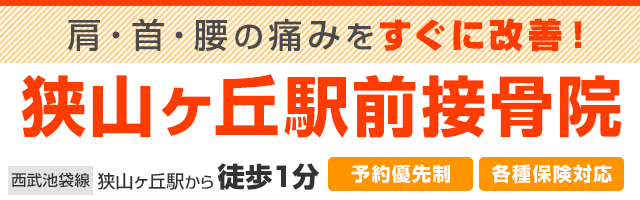オスグッド

こんなお悩みはありませんか?

朝歩き始めた際に「膝の違和感」がある膝の動作開始時に痛みが出る
膝が完全に曲がらない、伸びきらない、しゃがむ動作や階段の昇り降りがつらい
膝周辺に腫れや熱感を感じるようになり、むくみや重だるさを感じる
膝に「ゴリゴリ」とした違和感を感じる
日常生活に支障をきたすほどの痛みが続き、活動範囲が狭くなり、体重の増加や気分の落ち込みがある
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッドとは、主に膝の成長軟骨が引っ張られて剥離し、痛みや腫れが生じる状態のことを指します。
この「成長軟骨」とは、成長期(おおよそ0歳から17~18歳頃)に見られる長管骨(腕や脚の骨)の端に存在する軟骨で、成長とともに徐々に骨へと変化していく部位をいいます。
オスグッドは、太ももの前側にある大きな筋肉「大腿四頭筋」が、成長途中にある膝の下の付着部(脛骨粗面)を強く引っ張ることによって起こります。この繰り返しの負荷により、脛骨粗面が剥がれやすくなり、痛みや腫れといった症状が現れると考えられています。
特にジャンプや膝の屈伸動作が多いバレーボールやバスケットボール、ダッシュやキックの動作が頻繁なサッカーや野球などの競技に取り組む小・中学生に多く見られる傾向があります。
症状の現れ方は?

一般的に、スポーツ全般により症状が現れることがありますが、特にジャンプ動作や膝の屈伸が多いバレーボールやバスケットボール、ダッシュやキック動作が頻繁なサッカーや野球などにおいて発症しやすい傾向があります。
これらの動作によって、膝下にある**脛骨粗面(けいこつそめん)**と呼ばれる部分に限局された痛みが現れ、押したときに痛みを感じるのも特徴です。また、患部に熱感や腫れが確認されることもあり、横から見たときに骨が隆起しているように見える場合もあります。
初期には、正座や圧迫などによって脛骨粗面に伸張や圧迫のストレスがかかることで、痛みや違和感が現れるようになりますが、この段階では運動ができないほどではないことが多いです。
しかし、徐々に痛みが強くなってくると重症化する可能性があり、日常生活や安静時にも痛みを感じるようになることがあります。さらに、成長期を過ぎた後も運動時に痛みが残るなど、症状が長期間残存する場合もあります。
その他の原因は?

オスグッドと類似した症状「ジャンパー膝」について
オスグッドの鑑別疾患として、「ジャンパー膝」と呼ばれる症状があります。
これは、大腿四頭筋の柔軟性が低下することが要因のひとつとされています。特に、成長期の長身の選手に多く見られ、骨の成長に筋肉の発達が追いつかないことで、筋肉が硬くなりやすくなります。その結果、膝蓋骨(しつがいこつ)周辺に負担が蓄積されることで生じる慢性的な障害です。
このジャンパー膝は、好発年齢が12歳から20歳の男性に多い傾向があり、オスグッドよりもやや年齢層が高い方に見られるのが特徴です。
どちらの症状も、膝を頻繁に曲げ伸ばしするスポーツを行っている方や、筋肉の柔軟性が低い方に多く見られます。また、慢性化してしまうと、つらさの軽減が期待できるまでに時間を要するケースもありますので、なるべく早い段階での対応が望ましいとされています。
オスグッドを放置するとどうなる?

関節は、袋状の関節包と呼ばれる組織に包まれており、その内部には半月板や関節軟骨といった、衝撃を吸収するクッションのような組織が存在しています。これらの組織がスムーズに動くために、関節包の中は「関節液」という液体で満たされています。
しかし、体重や外部からの負荷が過剰にかかると、関節軟骨などの一部が剥がれ、そのかけらが関節液に混ざってしまうことがあります。その結果、関節内の滑膜(かつまく)が刺激を受け、炎症や痛みを引き起こすことがあります。
この状態が続くと、関節軟骨は徐々にすり減っていき、炎症も強くなる傾向があります。
最終的には、関節軟骨がほとんど失われてしまい、骨同士が直接ぶつかるようになります。
このような状態になると、膝が大きく腫れたり、安静時にも痛みが生じ、睡眠中に痛みで目が覚めてしまうほどのつらさを感じることもあります。
この状態を「変形性膝関節症」と呼びます。
この症状で施術を受けられている方は全国で約800万人とも言われており、自覚症状の有無にかかわらず、X線検査の結果からは約2400万人が変形性膝関節症と診断されているという報告もあります。
当院の施術方法について

当院では、膝の痛みに対する施術メニューとして「EMS(電気的筋肉刺激)」と「筋膜ストレッチ」をご提供しております。
その理由は、先にご説明したように、膝まわりの筋肉を適切に鍛えることで膝への負担を減らし、痛みの軽減が期待できるためです。
膝を支える筋力をつけるには、運動もひとつの方法ですが、「膝が痛くて歩くのもつらい」と感じる方も少なくありません。
そのような方には、電気の刺激によって筋肉を動かす「EMS」の施術がおすすめです。
体を動かさずに筋肉にアプローチできるため、無理なく筋力の強化を目指すことが可能です。
特に、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)を鍛えることが重要です。
施術の頻度や体調にもよりますが、EMSの施術と並行してウォーキングなどの軽い運動も取り入れていただくと、より効果が期待できます。
また、膝関節の安定には筋力だけでなく柔軟性も大切です。
そのため、当院では足まわりの筋肉にアプローチする「筋膜ストレッチ」を組み合わせ、柔軟性の向上にも取り組んでおります。
改善していく上でのポイント

膝の症状に対する対応方法について
膝のつらさに対する方法には「保存療法」と「手術」がありますが、まずは保存療法を行うことが大切です。
保存療法とは、薬物や運動による施術のことを指します。
薬物を用いた方法では、非ステロイド性抗炎症薬などを使用し、つらさの緩和を目的とした対症的な対応が行われます。
ただし、一時的に痛みをやわらげるだけでは根本的な負担の軽減にはつながりにくいため、運動による施術が欠かせません。
適切な運動を行うことで膝まわりの筋肉が鍛えられ、膝関節が安定し、負担の軽減が期待できます。
また、膝を動かすことで血液循環が良くなり、関節液中の刺激物質(発痛物質)も血中へ吸収されやすくなり、減少していくと考えられています。
さらに、運動によって体重をコントロールすることができれば、膝への負担はさらに軽減される可能性があります。
「膝が痛いから運動したくない」と思われる方が多いかもしれませんが、筋肉は使わなければすぐに衰えてしまいます。
長期間、動かない状態が続くと、骨盤まわりや腰部にも悪影響を及ぼし、将来的に日常生活に支障が出てしまうケースも見受けられます。
中には、介護が必要となるリスクを抱える方もいらっしゃいますので、それを防ぐためにも、無理のない範囲で運動を取り入れることが大切です。